2012年02月09日
2階から鯛焼き

ひさしぶりにデジカメのデータを見返していると、唐突な感じで鯛焼きの写真が出て来た。後には河原での美しい夕刻の風景が続く。ああそんなことあったなあと、2階で鯛焼きを食べたあの日を、たしかな情景とともに思い返す。
いくぶんの冷気をふくんだ風には、どこか冬の匂いがする。ヘルメットと頬に当たる風を感じながら、僕はいつもの道を、いつもとは違うきもちで走っていた。
目指す先はアリオというショッピングモール。ここは前職である人材派遣会社の社員時代、僕の主戦場だった場所だ。当時、勤めていた会社からこのモールへと大勢のスタッフが派遣されていて、僕はその管理・運営の命のもと、前社員時代の大半をここで過ごした。だから会社を辞めるときも、感覚的にはアリオを辞めるといった感じだった。
この鯛焼きの写真は、Web制作会社に入れることが決まったあと、ショッピングモールでお世話になった方々にそのご報告をしに行ったときのものだ。僕が働きながらWEBスクールに通っていることを知っていた人々は、心からのお祝いの言葉をくれた。直接の雇用関係はないのに、正直に言ってアリオで出会った面々の方が、実際の上司よりも僕にとってはるかに"上司"だったのだ。
いろいろな方々にご挨拶をすませたあと、なにをするでもなくモールをまわり、ベンチに座って今日会えなかった人たちに向けメールを打った。
しばらくして
「ここよろしいですか」
声をかけられる。初老の品の良いおばあさんだった。
「どうぞどうぞ」
そんな言葉をかえし、僕は携帯の画面へと戻る。おばあさんは隣にすわって鯛焼きを食べ始める。
車型のショッピングカートを押す若いおかあさんと、そのなかへと乗り込み"おもちゃ"のハンドルを握る子ども。放課後の高校生のカップル。ダンボールを抱え、小走りに通り抜けるどこかのお店の店員さん。たくさんの人が通り過ぎてゆくなか、僕とおばあさん、お互いだけはずっと動かずにいる。僕はいぜん携帯の画面を見つめているが、どこかにおばあさんと共にいる感覚をおぼえていた。
しばらくすると、
「あの...甘いもの苦手でなければ召し上がって。下のお店で買って来たばかりのもので...だいじょうぶですから」
遠慮がちな言葉と鯛焼きを突然差し出され、僕は戸惑ってしまう。
「ごめんなさいね。横にいられちゃ食べづらいわよね」おばあさんは細い声でそう言って、ベンチを立った。
「いえ...そんな。これ、ありがとうございます」 そう言うと、おばあさんは振り返ってぼくに小さく会釈をし、エスカレーターを下っていった。
僕はひざの上に伝わってくる鯛焼きのぬくもりを感じるうち、誰かとちょっとだけたわいない話をしたいような、そんな様子をおばあさんから感じていたことに気づく。
「世間話でもしながら、いっしょに食べればよかった」
そんな想いが浮かんできて、僕はおばあさんを探した。けれどもどの店先を探しても、もうおばあさんの姿はなかった。
結局、なんとなくそうするのが礼儀の感じがして、僕は2階の元のベンチに戻って冷めた鯛焼きを食べた。
暮れ色が人々の輪郭をぼやけさせ、かすみがかった空が濃いピンク色から薄い紫のもやへと変わる。青年が思いっきり振ったバットからボールが歓声と共に飛んでゆく。刻一刻と変わる河原の表情を眺めるうち、今だけしかない瞬間、その連続が人生なんだ、そんな当たり前の事実が心に浮かんだ。
するとあのおばあさんとの出会いが、なにかしら自分にとって意味を持つものに思えてきて、僕はすこし明るいきもちになってエンジンをかけ、ふたたび走り出した。




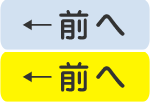
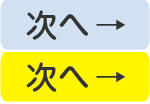
From X