2016年12月20日
居場所を築け

金曜、定時17時半。大きなフロアの一区画にむかって人がうごめき、やがておこる拍手の音。

僕が今働いている職場のフロアは、見える範囲だけでも200人分以上のデスクがある。働いている人が多ければ、それだけ退社する人も多い。だから月に1度くらいは、どこかしらでお別れセレモニーが行われている。まだここで働いて1年半の自分にとって、たいていは知らない人だ。
だが8月半ばの金曜日は違った。
盛夏のその日行われていたのは、Oさんの送別会だった。
【Farewell-MTG】と呼ばれるその挨拶が終わることは、ウェブデザイナーとコーダー、職種こそ違えど、自分にとっては最初から同じ部署に所属していた最後のメンバーがいなくなってしまうことを意味していた。

まあるい色白の小さな顔に、同じくまあるい大きな目を持つ彼女が、お別れの言葉を語り始めた。
あまり声が大きくない彼女の話を聞こうとあたりが静かになる。その横顔を眺めているうち、僕の心に彼女についての情景が、ある感慨をもって描き出されるー
ー浮かんできたのは同じく彼女の横顔だった。
それは僕がこの職場で働くようになって、初めて出席した会議でのことだ。会議とはいっても、僕が所属することになったAさんチームのメンバー9人がちいさな会議室に集い、それぞれが今どんな仕事をしているかを報告し合うだけで、形式張ったものではなかった。
にも関わらず、僕はガチガチに緊張していた。そんな緊張する僕の向かいで、彼女は頬杖をついて、ガムを噛みながらスクリーンを見ていた。
文章にすればそれだけのことだ。
なのに彼女が帰国子女で、異国で暮らしていたという事前情報と相まって、プロジェクターの青白い光に照らされたOさんの横顔は、僕の目には自分とは全く違う世界の住人のように映ったことを印象深く覚えている。
Oさんをはじめ、会議でのチームメンバーの話し振りはじつにスマートで、なんだかキラキラしていて、僕だけがその場にいる準備が整っていないように感じた。
僕が豊島区・南大塚で牛乳を配っていたとき(僕は若かりしころ、4年も牛乳配達の仕事をしていたのだ)に、Oさんはアメリカで映画みたいに、英語で恋愛とかしていたのかな...などと勝手に考えた。
その会議のあと、彼女の作ったデザインを、いくつか僕がコーディング(プログラミング)する機会を得た。
彼女のデザインをコンピュータースクリーン上で再現しようと仔細に見るたびに、僕はOさんを器用な人と感じた。それは手先が器用ということではなく、いやもちろん僕よりは圧倒的に器用だろうがそうではなく、制作依頼者がデザインを通してユーザーに伝えたいものを掴み取ってかたちにする感覚と、なによりそのスピードだった。
彼女との仕事はいつも、Oさんのデザインが完成された後に僕が仕事を開始する、いわば請負型だったが、この夏最後に共に取り組んだ案件だけは別だった。
ディレクターとしてロシアからつい先日、日本へと帰化したハンサムガイのSゲイくん、コーダーの僕、そしてデザイナーのOさん。3人であるキャンペーンサイトを作ることになった。
いつもはいわば完成された設計図であるデザインデータを手渡されるポジションの僕にとって、設計図そのものからみんなで作り出す作業はとても新鮮で、僕はひさしぶりに仕事にたいしてワクワクする気持ちを覚えた。3人よらば文殊の...ではないが、トリオでいろんな知恵を出し合い、デザインは次々にかたちを変えていく。
僕にとって、もうひとつとても新鮮だったことがある。
それはOさんが常に迷いながら、作業を進めていたことだ。
彼女が加えた変更で良くなったこともあれば、その逆もあった。
二歩進んでは一歩さがる...水前寺清子の歌のように、デザインはいったりきたりを繰り返しながら、少しずつブラッシュアップされていく。その様子を、僕は間近でずっと見ていた。
ーOさんのお別れの挨拶は、新卒として入社したころに始まり、研修としてビックカメラで売り子をしていたエピソードや、その研修期間を経て自分では思いがけないデザイナーという職種に配属された話へとつづいていく。
実際には会ったことがない、新卒時代の彼女を頭に思い描きながら「社会のなかで、自分の立場や居場所を作るって、誰にとっても相当タフなことだよなぁ」なんてことを改めて思った。

お別れの挨拶とそれに続く写真撮影が終わると、仲のいい仲間がOさんを取り囲んだ。僕はそんな輪をはずれて会社の外へと出る。
真昼が永遠に続くかのごとく照りつけていた陽は、いつしか夕刻のそれへと変わっていた。
のんびりと二子玉川駅まで歩く僕のよこを、肩車をされた女の子が追い越して行く。女の子の小さな手は、振り落とされないようお父さんのスーツの肩を必死につかんでいた。
会社前の広場につくられた仮設のビアガーデンから、サラリーマンたちの笑い声が響く。
夕焼けの街には、金曜日の喧噪のなかに、どこか真夏のピークが去ったような寂寥感がまじっていた。
▼この曲を聴くと、特別暑かった今年の夏と、Oさんのことを思い出します



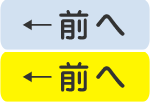
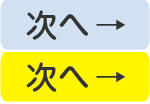
From X