2021年07月11日
心の木ー僕のみっともない生存戦略

7月11日「セブンイレブンいい気分」の今日は、僕の誕生日だ。
最近も書いたことだけれど、このブログにあげている文章は、読んでくださる方への『手紙』に見立て、文章を書いている。
僕の身の回りに起こったできことを、僕の目と心を通して、できる限り【深く、鋭く、そして温かく】伝えたい。
そう思って書いている。
なにを言いたいかというと、それが実現できているかは別として、僕は僕なりに読み手の方のことを考えて、書いているつもりだということだ。
だけど誕生日の今日だけは特別で、自分のエゴを貫いて、自分が書きたいことだけを書こうと思う。
自分や家族の本当にみっともない話を書くので、それをあえてネット上でさらすことにご不快になられる方もいらっしゃるかもしれない。
また、きっと母はこの文章を目にするだろうし、父の耳にも、なにかのおりにこの文章の話が入るだろう。
特に世間体を気にする父は、激怒し、生涯僕と口を聞かないことになると思う。
それでも書きたいと思うのは、これを書き、晒すことが、今の自分にとって、真に必要なことだと思っているからだ。
箇条書きで、支離滅裂な文章になると思うが、今日の記事は、自分が自分のために今の想いを、文字として残した【公開メモ】だと思って頂きたい。
※すいません。読んでいる途中でご不快になられた方は、どうか今日の記事はスキップしてください。
また明日から『令和の青』に来て頂けることを願っております。
→
僕は17才のころから、つい3年ほど前まで、2週間に1回、精神科のカウンセリングに通っていた。
高校2年生のとき、初めて精神科のクリニックに行き、さまざまな心理分析のテストを受け、世の中には強迫神経症という病があり、自分はその重度の患者ということを知った。
そのときに医師から言われたのは「失礼ながら、よく生活していらっしゃる。そういう状況だ」という言葉だった。
その言葉を聞いてまず初めに感じたのは、見つけてもらったという安堵の思い。
そして自分が精神科医に最初に返した言葉は「どれぐらいの期間で治るか?」という問いだったと思う。
この問いに対して「どんなに早くても10年」と医師は告げた。
それから「どんなに早くても」という言葉の意味を、ひとつ、ひとつ丁寧に説明してくださったと思うが、僕は早くても10年という言葉に絶望し、先生の話が、ほとんど頭に入ってこなかった。
ーすぐには治らない。これは長い長い戦いになる。
僕の闘病生活は、このとき先生が話してくださった言葉の意味を、改めて理解し、受け入れていくことから始まったと思う。
→
強迫神経症がどんな病かは、興味があったら調べて頂くとして、ほんとうに苦しかった。
僕の13,4才から約10年間は、自分がこの【神経症の患者であること以外はなにもない】文字通り、そんな日々だった。
お世話になっている医師から「重い強迫神経症に罹っている患者は、誰もが世界で1番自分が苦しいと思っている」といった内容のことを何回も耳にしたが、ほんとうにその通りだと思う。
仕事、勉強、運動、人間関係、基本的な生活、恋愛、夢...この病は、人生のあらゆることに、甚大なるマイナス影響を与える、業病だ。
人生で最も多感な十数年に、頑張りたいと思っても、自分の体が、自分が思うように動かせず、努力できないという現実は、ほんとうに言葉ではたとえようのない苦しみの連続だった。この病気のために、それこそ数え切れないほど、惨めな思いもした。
→
神経症の苦しみがイメージができない方に、この症状の苦しさを端的に伝える例えとしては【酷い吐き気が常にある】と思ってもらうのが、1番イメージしてもらいやすいように思う。
吐いて一瞬だけ楽になったり、眠っている間だけほんの少し苦しみを忘れられたりするが、目覚めと同時に激しい吐き気がまた襲ってくる。
しかも吐き気に襲われていることを、まわりには理解してもらえない。
その状態のなかで、仕事をしたり、勉強をしたり、スポーツをしたり、誰かと話をしたり...といった日常生活を過ごさなければならない。これはまさに地獄絵図の日々だった。
当時からよく死にたいと思っていたが、正確にいうと、死にたいというよりは、もう起きたくないというのが、率直な思いだった。
起きてまたあの際限なく襲われる、吐き気だけの世界へと戻りたくない...いつもそういう風に思い、当時は可能な限り、寝てばかりいた。
→
まじめに治療に取り組んだこともあり、さいわいにして24才くらいから、ほんとうに少しずつ症状が軽くなってきた。
だがこの病は、一気に晴れ渡るように苦しみから解放されるわけではない。
吐き気(症状)がおさまってきたあとは、それと反比例して、強烈な吐き気によって人生が停止していた、十数年の遅れを取り戻すための戦いが始まった。
その人生レースは今もなお、続いているように思う。
→
お恥ずかしい話だけれど、僕は1年以上前から、自分の家族とは絶縁状態にある。
そしてこれはもっと恥ずかしい話だけれど、絶縁してからの方が、自分の人生は総じて健康的で、豊かなものになった。
僕はその事実をとても哀しいことだと思っている。
僕の両親は、世間的に見れば育った環境や学歴など、いわゆるインテリ層と呼ばれるような部類といえると思う。かつ、父も母も一級建築士でもある。
息子の自分がいうのもなんだけれど、それなりに信頼される社会的地位に身を置いている、といえるだろう。
だがそうした立派な世間体とは裏腹に、父親はモラハラが人のかたちをしているというような人物だった。
また自分にとって母は、残酷なほどに、人の気持ちを思いやれない人だった。
→
これはまだ世の中がコロナ渦へと突入するすこし前のことだが、父があまりにも日常的に大きなくしゃみや咳を撒き散らしているので、弟が「(風邪などウイルス性起因の咳ではないとしても)エチケットとしてマスクはして欲しい」といったことを、弟なりに言葉を選んで、父にお願いしたことがあった。
父はその弟の発言に激昂し、以来2年近く、自宅ではなく近所の仕事場にこもって生活をし、食事は母に事務所まで運ばせ(父に言わせれば勝手に母が運んできた...なのだが)家族とはいっさい口を聞かずに暮らしていた。
これはささいな一例に過ぎないが、自分が気に食わないことがあれば「俺は不満だ」ということを、態度や無視することでしか示せない。
ほんとうに「一事が万事」そんな感じの人だったので、僕は物心がついたころには、父親を怒らせないように、機嫌を損ねないように、常に気を使って、ビクビクしながら生きていた。
→
一方でそんな父を、僕はどうしてもストレートに憎みきれなかった。
その想いは大人になるにつれ、自分でも不思議なぐらい強くなった。
それは父の母、祖母がどんな人かということ、子供があんな母親を持つことがいかに不幸であるかを、歳を重ねるごとに理解していったからだと思う。
端的にいうと、祖母は自分が50年以上連れ添った夫(自分の祖父)が亡くなった葬式でさえ「自分の趣味の日本舞踊の練習をしたいから、私は出席しない。あんたたちで勝手にやってくれ。ただし金はなるべくかけてくれるな」と、冗談ではなく本気でいうような、身勝手な人だった。
またお金への執着心は、異常と思えるほどだった。
自分の祖母がどのような来し方を経て、このような人を人たらしめる、最低限の愛情さえ、欠落した人格になったのか、僕には今でも分からない。
ただ僕に分かるのは、自分がこのような母親を持ったら、間違いなく人生は狂い、自殺など破滅への一途を辿ったということだ。
おそらく父は、自分でも無意識なうち【鈍くなる】ことで、自分を守っていたのだろう。
今でもその一点では、ほんとうに父親に哀れを感じ、同情する。
僕が幼いころは普通の父親だった父が、小学校4年生の終わり頃から、僕に対しての当たりが急激に強くなったのは、その年頃が、男の子から男へと変わりはじめる段階だということと、無関係ではないと思う。
それを感覚的にわかり、同情してしまう気持ちが、父をストレートに憎むことにブレーキをかけていた。
→
長年お世話になり、僕が信頼している精神科医の先生から「人の心というのは、心を植物、その植物を育む日光や水を愛情にたとえると、もっとも理解しやすい」という説明を、何度か聞いた。
「日光に当ててやらなければ、あるいは水をやらなければ、すぐに枯れてしまう。
だからといって水をやみくもに与えては根を腐らせてしまう。
野放しにするのはもちろんダメだが、芽や枝がのびる方向を四六時中、強制しては、成長も萎縮してしまう。
初期の芽の段階はとくに重要で、芽生えてから若木のころまでをしっかりと見守れば、あとは多少の問題があってもすくすく育っていく。
反対に最初に根を腐らせると、そこからやり直していくのは容易なことではない」
最近、よくその話を思い出す。
いせ(ひでこ)さんが、あそこまで木に惹かれ、取り憑かれたようになってるのは、本能的に「心の木」について、理解しているからに違いない。
当時の小学校1年生のころの僕には、この世にこんな痛みがあるのかを初めて知ったほど、痛かった。
痛みで熱が出て、冷や汗が止まらず、同時に吐きそうになったことを今でも覚えている。
当時の僕がなぜ、これほどの痛みを抱えても、病院に連れて行って欲しいと、それ以上は母にお願いできなかったには、僕なりの理由がある。
それよりすこし前に、起きてから具合が悪く、どうしても学校に行きたくない、行けないと思う朝があった。
「今日は学校を休みたい」と母に頼むと、「さぼるな、仮病を使うな」と叱られ、ふらふらになりながら学校に行った。
記憶の限りでは、おそらくは人生で初めて、休みたいと自分から言ったと思う。
だけど当時の僕は、子供なりに「自分はほんとうにいけないことを言ってしまったんだ。なんて悪い子なんだ」と思って、その日は学校に行った。
そしてやはり高熱にダウンして、学校を早退して帰ってきた、という出来事があった。
その経験が「病院に連れて行って欲しい」という一言を、心に押し留めた。
子供のころはずっと、母親に嫌われるのが、この世で1番恐いことだった。
→
その日まで普通にまっすぐついていた指が、麻酔なしに一目でわかるほどに曲がってしまったのだから、幼い僕には激痛だった。
今でもその痛みを身体が覚えていて、ストレスがかかったり、疲れがたまったりしたときには、写真のように必ずこの曲がった右手の小指から蕁麻疹が出て、それを合図に全身へと広がる。
→
この指の話はごく一例に過ぎない。
小学4年生のころにストレス(強迫行動)から、全力で走る自転車の車輪に足を突っ込んで、前歯が欠けてしまっても笑い話で終わってしまった。
19才のころに闘病の苦しみに耐えかねて、薬を大量摂取して自殺未遂をし、1週間意識がなくなったときも、その半年後には海外旅行へと母は出かけ、以降も毎年のように海外旅行に行ってしまったりと数え切れない。
→
僕は父親のことは、この人は変わらないと、とうに諦めていたが、母にはもっとなぜ息子がこのような病気になったかを、考えて欲しいと願っていた。
マザコンだと思うが、僕は母のことは諦められなかった。
家族の歪みが自分の病気として出ているだけで、これは僕だけの問題ではなく、家族の問題なんだと、母には真の意味で自主的に気づき、考えて欲しかった。
その思いから自分の覚悟を伝えたいと、『猫だもの』でも書いた、牛乳配達をして稼いだお金や、その後に6年遅れて大学生になったときもカフェでのアルバイトで、カウンセリング代を毎月、自分で賄っていた。
保健外診療だったため、毎月3万円ぐらいかかり、牛乳を1本配る毎に15円の報酬で働いていた僕には、ほんとうに高いお金だった。
通算すると、ゆうに250万円以上の医療費を、僕は自分で払っている。
→
その精神科医の先生が、自分の母について「物事を非常に甘く考え、腰が重いきらいがある」と言っていた。
その分析を聞いたとき、なんと端的に母のことを表しているのか、やはりプロだなと僕は感嘆した。
その先生の言葉を母に伝えると「自分のことを分かっていない」「失礼だ」と母は先生を非難し、激昂していた。
近年では、この精神科医に対して怒っているようすが、自分にとっては、ことさらに堪えた。
そしてこのときに、僕ははじめて、母のことを諦められたと思う。
小学校1年生の怪我した子どもを、骨折している可能性も容易に想定できたにも関わらず、近所の病院に連れて行けば普通に治ったにも関わらず、ここまで指を曲げてしまったことが「物事を非常に甘く考え」「腰が重い」以外のなんなのだろう。
僕が自分に子どもができて、たとえ怪我した直後に気づかなかったとしても、指が曲がるまで気づかなかったしたら(そんなことはしないと自信があるが)とんでもなく後悔をして、幾度となくそのことを考えるだろう。
僕が当時、どんなに痛かったか。自分の曲がった指に気づいて、どんなにショックだったか。
僕は病院に連れて行ってもらえるに値しないような人間なんだと、幼心に悲しく思っていたことにさえ、いまだに考えが及ばない。
しかもこの指の話は、ほんの分かりやすい一例に過ぎず、このような出来事が、ほんとうに大小、無数にあるのだ。
→
そんな母から
「病気が治るためにできることなら何でもする」「できることなら苦しみを代わってあげたい」
といった言葉を、僕は何度となく聞いている。
これもほんとうに苦痛なことだった。
何でもするどころか、最低限のことさえしてこなかったことの繰り返しが、子どもの心をねじ曲げ、破壊したことにさえ思い至らない。
自身の発言が、どんなに言葉の暴力なのかさえ、母はいまだに理解ができていないようだ。
今さらながら、謝りたい気持ちでいっぱいだ。
そしてその時代、その時代、自分にも価値があると思わせてくれ、大げさではなく命をつないでくれたガールフレンドたちに、深く感謝をしてる。
→
自分は小学生の頃、父親に「お前はいつか人を殺す」と、よく言われていた。
僕はほんとうにそうなるんじゃないかと、わりと最近まで、本気で心配をしていた。
ようやくその気持ちから解放されたのは「そんなふうに心配している人は、ぜったいそんなことをしない」と精神科医の先生に言われたからだ。
→
僕は子供の頃から「父親と離婚して欲しい」と、母にお願いをしていた。
書面の離婚などということはどうでもよく、とにかく物理的に距離をおかないと、自分の心がやられて壊滅状態になると、本能的に分かっていた。
でも幼い自分には別居とか、そういった知識はなく、離婚という言葉になっていた。
今あの子ども時代に戻っても、物理的に距離を置く以外、解決方法はないように思う。
→
話にとりとめがなくなってしまった。そろそろ筆を置こう。
僕は神経症に苦しんだ頃から治療の一環として「行動療法」という集中力を高めるための訓練を、通算で何千・何万回と繰り返し、2週間に1回必ずカウンセリングに通い、心を成長させてきた。
そうやって心を鍛錬してきたことが今、ITの仕事や、文章創作の仕事...あらゆることで、皮肉なことには、大きなバックボーンになっている。
→
どうしても顔を合わせる機会はあるだろうが、もう弟を除いて、僕は家族と、家族として会うことはないだろう。
弟のことは、自分にできる限りのことはしたいと思ってる。でももう、優秀な弟に対して、僕ができることはあまりないだろうな。
とにかく、自らの行動で、兄貴として【範を示す】ことだけは、していきたいと思っている。
→
自分なりに人生を巻き返すための戦略を立て、それを実際に行動で実現してきた。
振り返ると、そうした水面下でずっと続けていた努力が、この10年はようやくかたちとして現れてきたと思う。
ここ十数年で、働きながら学校に通って、ほんとうに0からITエンジニアの専門スキルを身につけ、徹夜徹夜の制作会社の日々を乗り越え、自分のブログを構築し、マイナビ出版のウェブ業界誌に1年半連載を担当するまでになった。
働きながらTOEICでもまずまずの高得点を取り、楽天のような大きな会社の正社員、それもグループ本部の、エリートの巣窟のような部署の一員にもなれた。
本も2冊出版し、今は3冊目を書き、並行して小説も書いている。
僕は自分が健全に生きていくために、家族を捨てた。
きっと僕は生きてさえいれば、これからもっと、もっと成長し、活躍できると思う。
そして活躍する度に、もっと寂しい気持ちになるだろう。






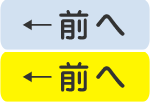
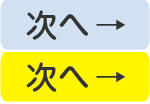
From X